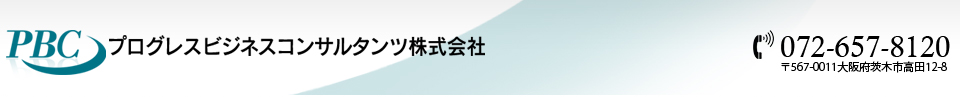日経ビジネス2019年1月7日号で「会社とは何かー組織と働き方の未来」という特集を組んでいましたので、それを参考に考えてみたいと思います。
会社の目的については一般的に『会社とは「事業」を行い利益を追求する法人』です。世界的経営学者のピーターF・ドラッカーは「企業の目的は
「顧客の創造」である」と定義しています。そしてドラッカーは「企業は社会全体の生命体」としてとらえ、社会を構成する組織や個人が、その社会
に貢献しているから社会が成り立つとしています。さらにドラッカーはすべての組織には3つの役割があると言います。
1 「貢献」と「成果」そして「人間の幸せ」
2 マネジメント層の3つの役割
1 自らの組織の特有の役割を果たす
2 仕事を生産的なものにし働く人たちに成果を上げさせる
3 自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに社会的貢献を行う
3 知りながら害をなすな
鋭い洞察と定義です。
日経ビジネスの特集号では、まずROE(株主資本利益率:収益性の指標)重視の経営だけではダメだと。非財務指標:社員や取引先、株主、顧客、
地域などバランス良く利益を配分しなければならない時代に入っていると。「会社は何のためにあるのか?」「信頼される仕事をしなければ組織
はもたない。そんな時代が来ている」と指摘しています。
ロート製薬では2016年に大手企業でいち早く副業の解禁、さらにはダブルジョブ制度を取り入れています。理由は社員に多様な経験をさせる、
社員の能力を最大限に発揮させること。一方で社内運動会や社員旅行を定期的に行って社員の団結を生み出しています。
ポストイットで有名な世界的企業3Mは世界200カ国に進出、9万人の社員が「世界中の深刻な社会問題を解決し、生活を改善していく」という
コンセプトをもとに仕事をしています。世界の名だたる企業が参考にする「15%ルール」「ブートレッギング(密造酒造り)」という研究方針が
あります。業務時間の15%を自由な研究や活動に使っていい、それも密造酒を造るように、こっそり隠れて。「顧客や社員、地域のことを考えて、
彼らを満足させなければ、株主にいい事なんて起きないだろう」と 3Mは60年増配を続けています。
東京大学の柳川範之教授は、次世代の「会社」の意味を「人と人がインタラクション(相互作用)する場所」と定義しています。組織形態は
クラシック型とロック型に分化するというのです。クラシック型は1つの古典的楽曲の演奏を極めていく。従来の日本の会社です。それに対しロック型
は時代に合わせ新曲を作り続けなければならない。デジタル化など変化の時代に先進国の多くの産業はロック型でなければ生き残っていけない」と。
いづれにしてもフラットでオープンな組織、社員の自主性や創造性、働きがい、やりがいを育む機動的な組織が伸びていくと思います。