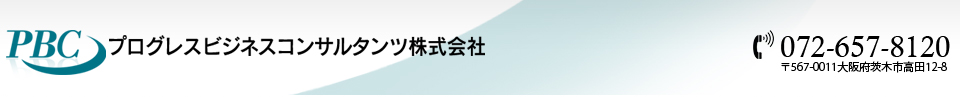M&Aはなかなか難しい経営課題です。特に業種を超えてM&Aを行う場合は難易度が一段と上がります。世間で多くの成功失敗の事例もあり、今回は日経ビジネス2018年11,05日号で「失敗するM&A、成功するM&A」という特集を参考にM&Aを考えてみます。
日本企業のM&A成功率についてはデトロイトトーマツコンサルティングが2018年5月に発表した調査結果によると海外M&Aで37%、失敗が21%、どちらとも言えないが42%になっています。国内でも同様にこの成功率が1つの目安になると思います。
一般的にM&Aを成功に導くには「事前準備」「条件交渉」「買収後の統合作業」の3つの関門があります。
事前準備はM&Aの交渉前の準備のことで、M&A対象企業のデューデリジェンス;資産査定と既存事業とのシナジー効果、自社の成長戦略と合致しているかなどの検討を行います。買収巧者として名高い日本電産の永守重信会長はこれまで60件のM&Aを手掛け、その多くで結果を出されていますが、毎年、年末になると買収を考えている企業のトップに「会社を売るときには声をかけてほしい」と手紙を書かれているそうです。手紙をもらった企業経営者が「売り時」と感じた時には、真っ先に日本電産の永守会長を思い浮かべるそうです。買収案件の交渉には「相対」と「入札」があり、入札はライバルとの競り合いになるため価格がつり上がりやすいわけです。その意味では「相対」が好ましいわけです。
出合い頭は失敗の下、常日頃からアンテナを張って独占交渉が望ましいと思います。特に銀行、証券会社からの持ち込み案件には注意が必要です。
条件交渉で最大の焦点は「買収価格」になります。基本は「相手のことを正しく知らなければ正しい値段はつけられない」ことです。デューデリジェンス(DD)は財務諸表などを分析する財務DD、他には法律面、税務面など様々な角度から分析が必要です。DDを怠ると買収後「減損計上」につながる場合があり、特に気をつけないといけないのは、M&Aありきで、それを正当化する戦略を考え出し買収に走ってしまうことです。投資ファンドは撤退ラインが徹底していて、企業を買収した後改革を施し、5年程度のあと売却して利ザヤを得るのが投資ファンドです。余りに熱くなって高値で買うと将来売却しても利益が残らないことがあります。やはり「撤退ラインを事前に決めておく」ことが大切です。さらにM&Aが成功できるためには、「聞く耳を持つ経営者かどうか」「相手先との一体感があるかどうか」「トップ自らすべての交渉をせず交渉担当者に任せる」ことがポイントになります。
統合作業は買収後の統合作業(PMI)のことです。買収したことで「市場を買えた」「時間を買えた」と満足してはいけないのです。特に「日本企業は企業が持つ製品などを見て買収を判断しがちですが企業を経営するのは人。トップの素質は投資決定のかなりの要素を占める」という識者の声があります。統合作業では買収先企業の経営陣や従業員とどう一体感を持たせ、生かすのに工夫し、担当者がいかに圧倒的な統治者意識を持てるかがPMIの成否を決めると言われています。結局最後は相互の信頼感がM&A成功の秘訣だと思います。