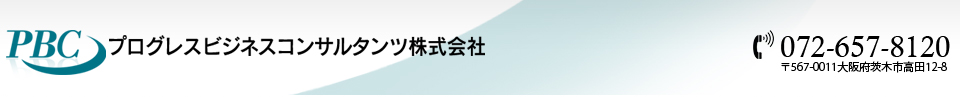幾度もピンチをくぐり抜け、それを糧に成長を続ける企業がある。一方で、たった一度の危機で衰退を始める会社も少なくない。
両者の差は危機を好機に変える「4つの技術」の有無にあるという(日経ビジネス2020、10,26日号参照)
1 動揺を防ぐために「遠大な視野を持つ」
「ピンチをチャンスに変える」とはどういうことかと言えば“危機に直面することで、平時では現れない組織の潜在能力を
顕在化させ、危機以前よりも強い状態になる”ことだ。組織であれ個人であれ、これを実践する大前提となるのが「ピンチ
でパニック状態にならないこと」(脳科学者の岩崎一郎氏:ピンチになれば視野が狭まる)組織が動揺すれば危機を好機
に変えるどころではなくなる。これを防ぐ有効な方法が「長期的な視野に立つこと」「最悪の事態を想定する」「逆算し
て行動を決める」簡単な例で言えば、リーマン・ショック級の市場暴落が起きても「人類の経済は、曲折を経ながらも、
拡大し続ける」との長期的視点を持つ投資家は狼狽(ろうばい)売りをしない。企業経営も同様で「目の前の危機が遠大
な目標にたどり着く過程の曲折の一つ」と経営陣や社員が信じている会社は、ピンチに動じることはない。
2 反発力を高めるために「社員の自己肯定感」
ピンチをチャンスに変えるため、次に必要になるのが社員の自信だ。劣勢を覆し、しぶとく攻撃にまでつなげるには当然、
普段は使わない強い反発力が必要になる。そのベースとなるのは「自分たちはできる」という現場の自信以外にない。
それには「自社の強み・弱みを具体的に何なのかを再認識する」「ミッションを明確にする」「自信を持つ」ことと
「危機感の共有」が大事になる。
3 苦境を打開するための「他者を巻き込む風土」
危機的状況で火事場のばか力を発揮するには、社員一人ひとりの自信に加え、団結力も欠かせない。ピンチは誰にでも、
どんな起業家にも訪れる。それを乗り越えるためにもビジョンやミッションへの賛同者をどれだけ増やせるかが重要と
なる。「抱え込まず、周囲と連携する」「外向きの目を大切にする」「危機感、すべきことを共有する」そして現場が
自律的に会社を動かすことが大事。
4 スピード感を育むための「現場優先の意思決定」
危機を好機に変えるためには、もう1つ、必要な要素はスピードだ。もちろんお互いを信頼し合うことも大事。ピンチで何も
しなければ経営状態はますます悪化する。一刻も早い経営判断が必要で、そのために有効なのが現場優先の意思決定をすることだ。